

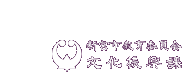


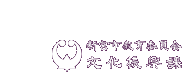
| 目 | 科 | 和名 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|
| 甲虫目 | オサムシ科 | キイオサムシ | 紀伊半島基部にすむイワワキオサムシの亜種で、熊野の森に普通に見られる。 |  |
| オオダイオオナガゴミムシ | 大台ヶ原から熊野に分布する大型のナガゴミムシ。水際の石の下などに見られる。 |  |
||
| センチコガネ科 | ルリセンチコガネ | オオセンチコガネの地方型で、紀伊半島のものは体が強い青藍色に輝くのでこの名がある。糞を転がす習性がある。 |  |
|
| コメツキムシ科 | オオダイルリヒラタコメツキ | 金属光沢のある緑色の美しい種。大台ヶ原から熊野にかけて見られるが少ない。県レッドデーターブックでは絶滅危惧Ⅱ類。 |  |
|
| テントウムシダマシ科 | セダカテントウダマシ | 紀伊半島の山地の朽ち木に生えたキノコ類に集まる。 |  |
|
| カミキリムシ科 | ナンキセダカコブヤハズカミキリ | セダカコブヤハズカミキリの熊野亜種。大塔山系・大雲取山系からのみ見つかっている。 |  |
|
| 鱗翅目 | シジミチョウ科 | ナンキウラナミアカシジミ | 熊野特産の亜種。基種ウラナミアカシジミがクヌギを食樹とするのに対し、本亜種はウバメガシを食樹とする。 |  |
| 目 | 科 | 和名 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|
| 甲虫目 | クワガタムシ科 | ルイスツノヒョウタンクワガタ | 四国南端・九州南端・南西諸島から知られていたが、近年熊野の海岸林から発見された。一生を朽ち木の中で過ごす。黒潮に運ばれ移住したものと考えられる。県レッドデーターブックでは絶滅危惧種Ⅱ類。 |  |
| マメクワガタ | ルイスツノヒョウタンクワガタとともに、紀伊半島沿岸を分布の北限とする。朽ち木の中で過ごすが、灯火に飛来した例もある。 |  |
||
| 鱗翅目 | アゲハチョウ科 | ミカドアゲハ | 紀伊半島南部の神社林のオガタマノキで発生する大型のチョウで、四国高知県では天然記念物に指定されている。南西諸島が分布の中心。熊野は分布の北限になる。 |  |
| ナガサキアゲハ | 近畿地方を北限とする。近年熊野ではごく普通に見られるチョウの1種となった。 |  |
||
| タテハチョウ科 | イシガケチョウ | 紀伊半島を生息の北限とする。幼虫はイヌビワを食し、熊野では近年個体数が増えている。 |  |
|
| マダラガ科 | サツマニシキ | 南西諸島・九州・四国・紀伊半島・中国地方北部に生息。亜熱帯性で極彩色の美しいガ。幼虫はヤマモガシを食べる。成虫は8月から10月にかけて昼間飛ぶ。 |  |
|
| オキナワルリチラシ | 南西諸島から九州・四国・紀伊半島沿岸部に生息する美しいガ。山口県や島根県の沿岸部でも見つかっている。幼虫はツバキなどを食べる。 |  |
||
| ゴキブリ目 | マダラゴキブリ科 | サツマゴキブリ | 九州南部以南が生息地であったが、近年熊野地方で見られるようになった、森林性のゴキブリ。成虫も飛ぶ翅が無く、古代三葉虫を思わせる。 |  |
| 半翅目 | キンカメムシ科 | オオキンカメムシ | 熱帯アジアから日本にかけて見られる派手なカメムシ。大移動をすることで知られ、日本各地で見られるが、房総半島以西の沿岸林で越冬する。熊野でも冬季ツバキの葉などに群がって越冬するのを観察できる。 |  |
| 目 | 科 | 和名 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|
| 甲虫目 | コブスジコガネ科 | アイヌコブスジコガネ | 体長1cmほど、山地のカモシカやタヌキなど動物の死体に集まる。大塔山や大雲取山系で見つかっている。 |  |
| 半翅目 | キンカメムシ科 | アカスジキンカメムシ | ヨーロッパ・シベリアを経て日本列島に分布。メタリックグリーンに赤い筋模様と見るからに存在感があり、オサムシの色彩を思わせる。北方系でありながら、熊野の暖かい地に見られる。 |  |
| カメムシ科 | ツノアオカメムシ | メタリックグリーンの美しい種。北方系で山地のミズナラやシラカバ、ニレなどの樹上で見られるが、熊野ではかなりの低地からも見つかっている。 |  |
|
| エゾツノカメムシ | 名前の通り北方系の種。熊野では山地のミズキなどから見いだされる。 |  |
||
| 蜻蛉目 | サナエトンボ科 | コサナエ | 近畿地方では日本海側と紀伊半島東部に特異な分布を示す。休耕田の湿地などにみられ、本宮町から古座・古座川町にかけて見られる。 |  |
| エゾトンボ科 | オオエゾトンボ | 北に分布の中心を持つエゾトンボの亜種。山地のため池や休耕田の湿地などで見られる。 |  |
|
| 目 | 科 | 和名 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|
| 甲虫目 | クワガタムシ科 | アカアシクワガタ | ブナ林やアカガシなどの照葉樹林で見られる。ヤナギの樹液に集まったり、灯火にくることも知られている。 |  |
| ヒメオオクワガタ | ブナ林で見られる。晩秋ヤナギの細枝に集まることが報告されている。 |  |
||
| オニクワガタ | ブナ林で、朽ち木や倒木上で見られる。 |  |
||
| コガネムシ科 | オオチャイロハナムグリ | モミやツガ、スギなどの大木の洞の中にすむ。大木の伐採が進んでいる今日、生息地がせばめられている。県レッドデーターブックの絶滅危惧種Ⅰ類。 |  |
|
| オオキノコムシ科 | オオキノコムシ | 体長2cmを超す大型種で、ブナの枯れ木や、多孔菌のキノコに見られるが少ない。県レッドデーターブックの準絶滅危惧種。 |  |
|
| ヒラタムシ科 | ルリヒラタムシ | 体が扁平で、枯れ木の樹皮下にすむ。個体数は少ない。似た種に、上翅が赤く小型のベニヒラタムシ、エゾベニヒラタムシがある。県レッドデーターブックの準絶滅危惧種。 |  |
|
| コブゴミムシダマシ科 | アトコブゴミムシダマシ | 山地の朽ち木につくサルノコシカケなどのキノコに見られる。特異な形をしている。 |  |
|
| カミキリムシ科 | ルリボシカミキリ | 美しい種。ブナやカエデなどの倒木や伐採木などに集まる。 |  |
|
| ヨコヤマヒゲナガカミキリ | ブナ林と切っては考えられない種。全国的にも稀種。県レッドデーターブックの絶滅危惧種Ⅱ類。 |  |
||
データ提供 熊野自然保護連絡協議会 南 敏行